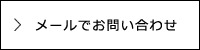トップページ > テーマで探す > しごと > #3 農園の仕事をテレワークで支える 【糸島しごと】
#3 農園の仕事をテレワークで支える 【糸島しごと】
更新日:2025年8月21日
#3 農園の仕事をテレワークで支える

わかまつ農園 パート従業員(雇用型テレワーカー)
1980年、福岡県大牟田市生まれ。看護師として福岡市内の病院に10年勤務した後、出産を機に退職。2015年糸島市に移住し、現在は2児の子育てをしながら糸島市二丈吉井の「わかまつ農園」にテレワークで勤務している。
農薬や化学肥料に頼らない有機農法で果樹や野菜を栽培し、農作物を使った製品の加工・製造、販売までを一貫して行っている「わかまつ農園」。2021年には農園直営のカフェ&直売所「お菓子と暮らしの物 りた」をオープンするなど、独自の農業スタイルを展開している。
中村さんがわかまつ農園と出会ったのは、糸島市でライターとして活動を始めた2018年。未来を見据え進化する同農園と共に、自身も業務委託のライターから、テレワークで勤務する「雇用型テレワーカー」へと働き方を変え、現在は幅広い業務をこなす。「常に新しい事に取り組ませてもらっています」と明るく語る中村さん。柔軟な働き方で、経験とスキルを生かし活躍する中村さんの「今」を聞いた。
努力と経験の積み重ねで徐々にスキルアップ
農園にテレワークで勤務する働き方はあまり馴染みがないのですが、普段のお仕事の内容を教えてください。
多岐に渡りますが、大きく分けると事務とECサイトの運営ですね。
まず事務の内容としては、従業員の税務や労務に関する手続き、補助金の申請、社外からの問い合わせ対応やスケジュール調整など。農園が取材を受けた後には原稿の校正もします。
それから、ECサイトといういわゆるネットショッピングサイトの運営についてですが、サイトのページに、販売する商品の写真や魅力を伝える文章を作って掲載しています。文章の作成や校正にはライターのスキルがかなり活きていますね。

テレワークの様子。パソコンとスマートフォン、ネット環境があれば仕事に場所を選ばない
本当に幅広い。特に労務や税務は専門性が求められる分野ですが、経験があったのですか?
それがまったくなくて。けれど従業員の皆さんに迷惑をかけないよう、専門家のYouTubeの解説動画を見て勉強したり、税務署などに何度となく電話をかけたりして労務や税務に関する知識を増やしました。お金の計算に関しては会計ソフトの使い方を学びました。慣れるとそれほど難しくはないですよ。
マルチにお仕事をこなしているんですね。
周りからは「すごい」と言われますが、経験の積み重ねで今があるという感じです。
働きだした頃は、メールの返事一つにしても潤哉さん(わかまつ農園代表の若松潤哉さん)に確認や修正をしてもらっていました。だからいきなりここに到達しているわけではないんですよ。

「最初はパソコンにも慣れてなくて、
Wordの使い方から勉強しました」
と働き始めた当時を振り返る
農園と共に進化したワークスタイル
今の仕事に就いた経緯は?
糸島市へ移住して間もない頃、知り合いを増やしたくて、当時糸島市が主催していた「ママライター育成講座」を受講し、ライティングのスキルを学びました。講座修了後ママライターとして活動する中で、わかまつ農園が自社のWebサイトの記事を書くライターを募集していることを知り「スキルを活かすチャンスだ」と思って手を挙げたんです。
ライティングから始まったお仕事なんですね。
はい。初めの約2年間は、1記事〇〇円という報酬体系の業務委託で農園ライターとして、Webサイトに掲載する記事を作成していました。その後、2021年の「りた」オープンに向け社内の体制が変わり、潤哉さんの奥さんが担当していた事務作業を私が引き継いだんです。お店のレシート入力から始まり、年末調整、メール管理…とだんだん業務の幅が広がって。そのタイミングで、業務委託の農園ライターから、時給制の雇用型テレワーカーになりました。

直売所併設のカフェ「お菓子と暮らしの物 りた」では、自家製の食材をふんだんに使ったピザやドリンク、スイーツが味わえる

開放的で居心地の良い店内。木材置き場だった
建物を若松さん自ら改装を手掛けた
お仕事はどこで、どのようにしていますか?
コワーキングスペースに行くこともありますが、電話をすることが多く気兼ねしてしまうので、主に自宅で仕事をしています。パソコンとスマホ、ネット環境があればどこででもできるのがテレワークのいいところ。勤怠管理はアプリを使っていて、出勤ボタンを押したらカウントが始まり、休憩したい時にまたボタンを押す、という感じです。
出社することもあるのですか?
はい。2か月に1回程度、潤哉さんと「りた」で打ち合わせをします。話し上手な潤哉さんですが文章を作るのが苦手だそうで、私が考えや希望を聞いてそれを形にしています。例えば、潤哉さんが講演をする際には内容を聞いて私がパワーポイントで資料を作る、という具合です。お互いに得意分野で補い合って仕事をしている感じかな。ここでも、聞いた話を文章にするというライティングの技術が役に立っていますね。

打ち合わせの様子。若松さんは「由佳さんはとても優秀。由佳さんがいないとうちは完全に回らないです」と感謝を込めて話す

地元中学校のPTA会長も務める若松さん。「スーツはめったに着ないんですが、たまたま今日は視察があって」と朗らかに笑う
前職の、看護師の経験やスキルが生きていると感じることは?
仕事内容は違いますが役立っていると思います。看護師は常に優先順位を考えて動く仕事。今の仕事でも、いろんな会社からさまざまな内容のメールがきますが「これは明日」とか「これは急いだ方がいいな」と優先順位をつけたり、相談のタイミングを図ったりと効率よく仕事を進められています。
なるほど。今の仕事を成り立たせるために、大切にしていることや頑張っていることはありますか?
会社とは雇用関係にありますが、私は「雇われている」というより「会社がお客さん」という意識で仕事をしています。仕事の品質や効率を上げるため、専門書を何冊も読んで農業について勉強したり、自分のスキルを磨いたり。糸島市テレワークセンターが企画する講座や勉強会も、とても役に立っています。
最近受けた講座で役に立ったのは?
グーグルドライブの勉強会です。私が管理している社内資料のバックアップに手間がかかっていたのですが、勉強会で自動的にバックアップできる方法を教えてもらい「なんだ、こんなに簡単だったの」とびっくり。
他にも、「テレワーク推進講座」では、テレワークでのコミュニケーションのとり方や時間管理の仕方を学びました。今の会社ではテレワーカーが私だけなので、何もかも模索しながらやっていますが、他のテレワーカーのやり方を聞いて「こういうやり方もあるんだな」と、とても参考になりました。

「目標に応じた計画を立て、ああしてみよう、
こうしてみようと考えて動くのが好き」。
中村さんの仕事ぶりにはそんなチャレンジ精神が存分に発揮されている
「子育て最優先」で仕事も暮らしも充実
若松夫妻も4人の子育て中だと伺いましたが、同じ立場でよかったことはありますか?
とても助かることばかりです。
私は、子どもに持病があり通院や入院などのサポートが必要なんですが、潤哉さんも常に同じ目線で「子育てが最優先」と言ってくれます。私が入院に付き添う時は仕事ができる量も減ってしまいますが、理解してくれているという安心感が大きく、本当にありがたいです。
また、子どもたち同士も会うたびに仲良くなって、今では家族ぐるみで食事やカラオケに行ったり、おさがりの洋服を分け合ったりとプライベートでも一緒に過ごす事が多いんですよ。
暮らしと仕事がつながっているんですね。
そう!そこが今の仕事で一番気に入っているところです。
テレワークはどうしても職場の人間関係が広がりにくいですが、こうして時々会える距離でのテレワークなら交流もできるし、地域での新たなつながりも生まれます。糸島でのテレワークは私にとって、仕事と暮らしの両方においてメリットばかりです。
糸島での暮らしや子育てで気に入っているところは?
糸島の人は多彩で面白く、みんな糸島のことが大好き。それがすごくいいなあ、と思います。地域で活動する劇団の方が芸術に触れさせてくれたり、知り合いが自宅で飼育しているヤギやニワトリと遊ばせてくれたり。親子共に周りの大人たちからいろんな刺激をもらっています。糸島での暮らしは、そんな田舎の良さを感じられるほのぼのとした環境があることが気に入っています。

「子どもたちも、私がここで働いていることが嬉しいみたい」と中村さん。
子どもとの時間を最優先に、これからもテレワークを続けたいと話す
素敵ですね。最後に、今のお仕事において今後どうしていきたいですか?
「りた」を拠点に、若松夫妻がお客さんと接する機会を増やしたいと思っています。若松夫妻はとても魅力的な人柄の持ち主で、お二人に会うために店を訪れる人もいるほど。農園のシンボルのお二人に会えることで、お客さんの農園への親近感が強まって、わかまつ農園のブランド力を高めることにもつながると思います。農園のテレワーカーとして、今後テレワークでできる仕事をますます拡大して、お二人がもっと店に出られる体制を整えていきたいですね。
穏やかな口調で丁寧に話をする中村さん。優しい雰囲気の中にも、常に状況や物事を幅広い視点で考え、より良い方向へ変えていこうとする意欲と芯の強さが感じられる。「未来につながる農業」を理念に挑戦を続けるわかまつ農園と、高みを目指し努力を惜しまない中村さん、二者のタッグがこの上なく力強い。
(2023年11月取材、文=榮鮎子 写真=渡邊精二)