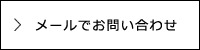トップページ > テーマで探す > しごと > #12「ホームホスピス」で最期まで安心して暮らせるまちに
#12「ホームホスピス」で最期まで安心して暮らせるまちに
更新日:2025年8月22日
#12 「ホームホスピス」で最期まで安心して暮らせるまちに
【記事(PDF版)はこちら】(PDF:2.5MB)
深川美香さん Fukagawa Mika
NPO法人マイレ理事長
1971年佐賀県生まれ。看護大学卒業後、内科、緩和ケア病棟に勤務。約10年、男の子3人の子育てに専念した後、2017年にNPO法人マイレを設立。訪問看護事業開始を経て、2024年4月に「ホームホスピス マイレの家。」を開所した。
「ホームホスピス」に出合い、「私がしたいのはこれだ!」と感動したという深川美香さん。ホームホスピスとは、自宅での生活が困難な人たちが、地域の中にある一軒の家で、介護のサポートを受けながら家族のように最期までともに暮らすこと。
看護師として訪問診療に関わった深川さんは、「住み慣れた地域で人が自分らしい生涯を送り、家族にも安心して看取ってほしい」という思いを抱き、訪問看護事業や地域の相談の場づくりを始め、2024年に念願の「ホームホスピス マイレの家。」を開所した。
「これからもずっと住み続けたい糸島で、最期まで人を尊重し、支え合える地域社会をつくりたい」と言う深川さんの働く姿や今後の展望を聞いた。
一人一人を尊重したサポートを大切に
深川さんはどんな仕事をしていますか?
NPO法人マイレの理事長として、糸島市二丈深江の「訪問看護ステーションマイレ」と、有田中央の「ホームホスピス マイレの家。」を運営しています。どちらにも毎日顔を出し、スタッフと状況や相談事を共有し、より良くなるように一緒に考えながら働いています。
NPO法人マイレは「人が生まれて死に逝くことは自然のことであり、尊いものだと感じられる、ぬくもりのある地域社会」を目指す法人です。「マイレ」はハワイ固有の植物の葉で「縁結び」などの意味があり、私もご縁を大事にしたいと思って、団体や施設の名称に使っています。
家の中央のリビングでスタッフからの報告を聞く深川さん
「訪問看護ステーションマイレ」と「マイレの家。」の二つを運営しているとのこと。それぞれどんな業務をしていますか?
訪問看護ステーションマイレは、私を含めて4人の看護師が在籍し、利用者のお宅に看護師が訪問して、体調管理や主治医の指示のもとで医療処置などをしています。
マイレの家は、ケアが必要な方々がサポートを受けながら、最期まで家族のように暮らすホームホスピスの住まいです。改築した一軒家に6人までの入居が可能で、健康状態や介護度、年齢などに関係なく利用できます。家の真ん中にキッチンとリビングがあり、個室にいても常に誰かと一緒にいる安心感があります。看護師や介護士、ヘルパーなどのスタッフが24時間体制で入居者さんをサポートしています。

入居者の暮らす個室で
優しく手を添えてサポート
「マイレの家。」では具体的にどのようなサポートをしていますか?
食事、入浴、体調管理など生活面のサポートです。入居者さんを尊重することを大切にして、それぞれの生活ペースと思考に合わせたケアを心がけています。
入居者さんの以前の職業や人柄を考慮した声掛けをしたり、食事はリクエストを聞いて作ったり。入浴も自分でできると言われる方は時間がかかっても見守り、必要時にサポートをするなど、家にいるような生活を送れるように寄り添っています。
ケアをしていて、困難を感じるときはありますか?
コミュニケーションがうまく取れない時や、入居者さんの要望であっても体調によって実現が難しいことがあります。その時は家族やスタッフ、ケアマネージャー、主治医などと一緒に悩みながら、最善の対応を考えます。
また、入居者さんと親しくなる分、看取り後に悲しい気持ちになるスタッフもいます。だから、スタッフみんなで入居の経過を振り返り、気持ちを整理する時間を設けるようにしています。そんな経験の一つ一つが、私やスタッフの成長につながっていると感じます。
入居者のリクエストで食事メニューを決める。
集まれる入居者のみんなで一緒に食事をしている
自分らしくいられる「ホームホスピス」をつくる
ホームホスピスをつくりたいと思ったきっかけは何ですか?
2013年に聞いた、ホームホスピスについての講演会です。
私は病院の緩和ケア病棟の勤務後に、約10年間子育てに専念し、2010年に看護師として復帰しました。ある時の訪問診療で、自宅で暮らす患者さんのいきいきした笑顔に感動したんです。そのときに住み慣れた場所で暮らす大切さを実感しました。
一方で、サポートがないと一人暮らしが難しい患者さんは、住み慣れた地域から離れざるを得ず、引っ越すこともありました。一人暮らしの患者さんには、訪問型のサービスだけでは十分なケアが行き届かない場合がある実状に、もどかしさを感じていました。
そんな時に、全国ホームホスピス協会理事長である市原さんの講演を聞く機会があり、ホームホスピスは地域の医療やコミュニティとつながり、安心して自分らしく暮らしていけるという話に、「私がやりたいのはこれだ!」と思ったんです。ホームホスピスが地域にあれば、長年住んだ場所で、馴染みの人との関係も切らずに、最期まで安心して暮らす選択ができると思いました。
ホームホスピス立ち上げのために、何をしましたか?
最初は自分で立ち上げるとは考えていなかったのですが、周りからの勧めもあってやってみようと決意し、2016年に市原さんに相談に行きました。当時は子どもが小さく、長期間の研修に参加できなかった私は、市原さんから「まず地域を耕しなさい」と、地域の人とつながる場づくりのアドバイスを受けました。そこで、誰でも生活の困りごとを相談できる場をつくったり、訪問看護を始めたり、地域とのつながりを広げる活動を行いました。
そんな中、2021年に遂にホームホスピスの研修に参加しました。ホームホスピスの場所探しでは、かつて訪問看護で伺っていた家を偶然借りることができました。地域を耕した結果が実を結んだんだと思います。
マイレの家のスタッフは現在13人。
笑いが絶えず、同じ志を持つ心強い仲間だ
糸島を最期まで安心して暮らせるまちへ
活動の拠点に糸島を選んだのはなぜですか?
きっかけは2011年の東日本大震災でした。
私は2004年に、海や山が身近にある自然豊かな糸島で子育てをしたいと思い移住しました。その後、看護師に復帰してまもなく震災が起こって。テレビで被害の様子を見る中で、もし糸島で災害が起こり避難所で暮らす時、自分には何ができるだろうとすごく考えました。その時から、自分がこれから最期まで住み続けたい糸島で、何か役割を持って地域に貢献したいと思うようになりました。
その思いが糸島でのホームホスピス設立につながったのですね。
現代の日本では、核家族化や単身高齢世帯の増加により、自宅で最期を迎えたいという本人の意思や、看取りたいという家族の希望があっても実現しにくい状況です。
家族に迷惑をかけないために、長年暮らした地域を離れて入院を選ぶ人もいます。支える家族も、家での看取りをしたくても経験がなく不安や戸惑いを感じる人が多いです。でも、訪問診療や訪問看護、私たちホームホスピスなどを頼れば本人や家族の意思や希望を叶えられると伝えたい。
糸島市をより「最期まで安心して暮らせるまち」にしたいです。
思いを実現するためにどんな活動をしていますか?
地域の人が誰でも参加できる学びや交流の場を開いています。例えば、看取りについて学べる「みんなの勉強会」や、認知症の方やその家族、それ以外の方も交流できる認知症カフェ「マイレカフェ」を開催しています。もっと多くの地域の人たちが、この活動の場に気軽に来てもらえるようにしたいです。
また、マイレの家の入居者さんと地域の人の交流も増やしたいです。マイレの家での様子を見て、地域のみなさんにも、一人一人を大事にしたケアや地域での看取りの大切さを感じてもらえたらと思います。
好物のジュースを差し入れしながら、入居者へ声掛け
糸島でこの仕事をする魅力は?
糸島はボランティア活動がすごく活発です。お互い支え合うことを大切にする人が多いのは、糸島の大きな魅力ですね。
例えば、家族が用事などで介護できない時に、患者さんの見守りをしてくれる在宅ホスピスボランティアの方がいます。マイレカフェでも「深江民謡」や「けん玉倶楽部」などのさまざまな方が、ボランティアとして喜んで活動に参加してくれます。本当にありがたいですね。
糸島は地域の方とのつながりを大切にする人が多いように感じます。そんな土地柄だからこそ、地域で手を取り合い、より「最期まで安心して暮らせるまち」になっていく可能性を強く感じています。
今後の展望を教えてください。
地域の人やボランティアの方々、私たちの活動に共感してくれる事業者と、もっとつながっていきたいです。お互いの思いを知り協力して広め合えたら良いですね。
これからも、自分の得意なことで貢献し、苦手なことは助けてもらい、最期まで人を尊重してみんなが支え合う地域づくりを目指したいです。目標は大きいですが、糸島でならできると信じて働いていきます。

入居者への敬意を大切に、家族のように接する
深川さんたちの明るい笑顔で、マイレの家は温かく包まれていた。地域での安心できる看取りの広がりを同じように願う頼もしいスタッフと共に、これからも地域とのつながりを広げていく深川さん。誰もが支え合える糸島へ、マイレの家から思いを発信していく。
(2024年12月取材、文=牧野登志江 写真=渡邊精二)