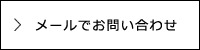トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 地域福祉 > 民生委員・児童委員について
民生委員・児童委員について
更新日:令和7年12月16日
民生委員・児童委員が改選されました
民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき、令和7年11月30日をもって3年間の任期が満了となり、12月1日付で全国一斉に改選されました。糸島市の定数は3人増の177人となりました。
任期は、令和10年11月30日までの3年間です。
「民生委員・児童委員名簿」は、このページの最下段の「関連ファイル」に掲載しています。
あなたの地域の身近な相談役
民生委員は、3年間の任期で厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。
児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。
例えば、こんなことで困っていたら相談してください
- 介護保険について
- 高齢者福祉サービスについて
- 障がい者福祉サービスについて
- 生活費について
- 子育てについて
- 一人暮らしで不安なことについて
注:民生委員には、民生委員法により、みなさまの秘密を守る義務がありますので、安心してご相談ください。
担当地区
民生委員は、それぞれ担当地区(受け持ち地区)があります。
連絡をとりたい場合は、担当民生委員をご案内しますので、糸島市地域福祉課(電話番号:092-332-2073)までお問い合わせください。