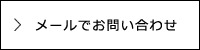トップページ > 市政情報 > 市の計画 > 各分野の計画 > SDGs未来都市 > SDGs認知・共感促進事業 > 【SDGs認知・共感促進事業】怡土小学校の取組を取材しました!
【SDGs認知・共感促進事業】怡土小学校の取組を取材しました!
更新日:2025年3月27日
糸島市は令和5年度に「SDGs未来都市」に選定され、「糸島市SDGs未来都市計画」に基づく取組を推進しています。SDGsの達成には、市民・団体・企業など、皆さん一人ひとりの行動が必要不可欠です。
そこで、令和6年度から令和7年度にかけ、「SDGs認知・共感促進事業」を実施することとしています。
市内で活動する市民・団体・企業等のSDGsに関する取組を取材し、情報発信することで、SDGsに関する取組の“認知”と“共感”を促し、SDGsに対する市全体の意識を高め、一人ひとりの行動変容につなげていくことが目的です。
令和6年度は、市内の各小中学校における取組を取材しています。
「SDGsとよく聞くけれど、具体的になにをすればいいの?」と疑問を抱かれている方も、今回発信していく取組を参考に、身近な課題の解決に向けた行動につなげていただければと思います!
- 「SDGs未来都市」選定時のページは、こちら
【怡土小学校】九大生の学習応援で「学ぶって面白い」を実感
井原山、高祖山などの山々に南東を守られた怡土小学校。豊かな自然環境、古代伊都国からの歴史や伝統文化を生かした教育が特長です。
「自立する怡土っ子の育成」を教育目標とし、自主的な学びを後押しする同校では、毎年5年生を対象に、九州大学の学生(以降、九大生)による学習応援「九大寺子屋」が行われています。この記事では、SDGsの17の目標のうち、「4.質の高い教育をみんなに」に通じる取り組みとして、令和6年9月の「九大寺子屋」の様子、子どもたちや先生の声、関わった九大生の思いなどをご紹介します。
義務教育下の子どもたちが、未来の自分を想像させる大学生たちから学ぶ意味や面白さを受け取る瞬間を、どうぞご覧ください。
九大生による学習応援「九大寺子屋」
(写真:ユニフォームをまとい、いざ教室へ)
「九大寺子屋」は平成27年からスタートした九大生と糸島市内小学生の交流事業です。小学5年生を対象とした取り組みで、令和5年度には市内の全小学校16校で実施されました。
次世代を担う子どもたちの学習意欲の向上や九大生、九州大学に親しんでもらうことを目的に、九大生が、自分の研究テーマや小学校での勉強が実社会でどう生かされているかを、分かりやすく子どもたちに教え、交流する事業です。
今回、怡土小学校でも、5年生を対象に授業が行われました。1組は法学部の時任さんによる「君も法律家になろう!」、2組は理学府の宮下さんによる「圧力を知ろう!」です。
各講師には3人のサポート役の学生がついており、担任や主幹教諭も適宜サポートをしつつ、45分間の授業をスライドや実験器具などを用いて進めていきました。
日常生活から「法律」への興味を引き出す…5年1組
「大学に住めますか?」「部活動はありますか?」など、子どもたちの質問タイムから始まった5年1組の授業。小学校から大学までの進学の流れ、九州大学はどんなところか、どんなことが学べるのかなどを、講師の時任さんが次々に説明。サポート役の学生たちも、今自分が何を学んでいるか、学ぼうと思ったきっかけなどをそれぞれ話しました。現役九大生の学生生活に、子どもたちは興味津々です。
(写真:大学ってどんなところ?)
続いて、本題の「法律とは何か」を学ぶ時間。法律が実際の暮らしにどのように関わっているか、子どもたち自身がグループで考え、意見を発表する学習です。
まず、時任さんが法律のイメージを子どもたちに尋ねます。子どもたちからは「守るもの」「怖い」「難しい」などの答えが出てきました。
すると、時任さんは「これらの法律はどんな内容だと思いますか?ヒントを基に考えてみましょう!」と問いかけ、「電気用品安全法・消防法」「食品衛生法・食品安全基本法」「道路交通法」の3つを子どもたちにイラスト付きのスライドで提示しました。子どもは各自で考えたことをワークシートに書き出していきます。
「消防って何を防ぐもの?」「どんな食べものだったら安心して買える?」「交通ルールってどんなもの?」と、時任さんがヒントを出すと、子どもたちは、「電気用品安全法・消防法」は家で火を扱う場面、「食品衛生法・食品安全基本法」はスーパーで買い物をしていた時、「道路交通法」は横断歩道を渡る時――というように、それぞれ自分の暮らしの中の場面を思い出しながら、ワークに取り組んでいました。
(写真:各自の意見をワークシートに記入)
ワークシートへの記入がある程度終わったら、次は各班でのグループトーク。班で話す法律をひとつ選び、その法律には何について書いてあるのかを考え、ワークシートに書いた各々の意見を持ち寄ります。消防法を選んだ班では「火や火事に気をつける」「材料が焦げないようにずっと見ておく」などの意見が挙がっていました。挙がった意見を各班で小型のホワイトボードに書き出し、黒板に貼り付けたのち、内容を全体へ発表しました。
子どもたちは、普段意識していないだけで、法律が自分の暮らしに既に生かされていることを学びました。
班内での意見を書き出す
各班の意見を黒板に貼って全体へ共有
次は、もっと具体的なルールについて考える時間。学校など身の回りにあるルールや当たり前に行われていることを、それが「法律で決まっていること」なのか、「こうしてほしい」「こうなるといいな」という思いによる「道徳」なのかを当てるクイズです。
「子どもの健康のために給食で牛乳を提供するのは、法律でしょうか?道徳でしょうか?」
時任さんの問いかけに、子どもたちは答えだと思う方に手を挙げます。その後も次々出される問題を「え~どっちだろう?」と熱心に考えました。
(写真:法律?道徳?選んだ方に挙手)
「理由を探してみると新しい発見や見方につながることがある」と伝えた時任さん。さらに、ルールを決める時に意識することとして、「大事に思うことは人それぞれ違うので、一人ひとりの考え方とその理由を大切にしてほしい」と述べました。
ペットボトルの実験で「圧力」を考える…5年2組
(写真:大気圧と水圧の実験器具)
5年2組では、九大生お手製の実験器具が登場し、歓声があがっています。身近な圧力「大気圧と水圧」の実験タイムです。2本のペットボトルを半分に切り、ふたを外した状態で上半分を逆さまにし、それぞれ鉄球とピンポン玉を入れて水を注ぐとどうなるか、という実験です。
鉄球とピンポン玉は浮くのか、沈んだままなのか、浮き沈みするのか、まずは子どもたちが結果を予想します。実験が始まり、子どもたちは水かさが段々増していくのを、固唾を飲んで見守ります。結果は、水に浮くはずのピンポン玉が沈んだままでした。
意外な結果に「予想が外れてビックリした」という子も。講師の宮下さんは、この現象には大気圧と水圧が関係していることを説明しました。
その他にも、身の回りの電化製品がもたらす現象と科学の関連を解説し、「当たり前のことに『なぜ?』と疑問を持ってみよう。それが科学の第一歩です」とまとめました。
(写真:学んだことをプリントに記入)
授業終了後、九大生を取り囲む子どもたち
「姿勢!これで5時間目の授業を終わります!礼!ありがとうございました!」
授業終了の号令が終わるとすぐに、子どもたちが一斉に講師やサポートを務めた学生を取り囲みました。お礼を言ったり、話したり、笑い合ったり、思い思いに交流を楽しむ姿がありました。学生が廊下に出ても、交流は終わりません。子どもたちの声に笑顔で対応する学生たち。「先生またね~!」帰っていく学生たちに手を振りながら、その背中を名残惜しそうに見つめる子どもたちの姿が印象的でした。
(写真:学生と話したくてたまらない子どもたち)
子どもたちの声
- 法律のクイズに全問正解できて、うれしかったです。質問コーナーでは、大学にも部活があること、大学の勉強のことをたくさん知ることができました。大学に行ってみたいです。
- いつもと違う感じの授業で楽しかったです。授業が分かりやすくて、先生たちも面白かったです。またやってほしいです。
- 目の前で実験をしてくれて楽しかったです。
- エアコンや蛍光灯など、身の回りにあるものが科学と関係があると知ることができました。
(写真:初めて聴く話に興味津々の子どもたち)
先生へのインタビュー
この取り組みに携わった主幹教諭の扇先生、5年1組担任の木下先生に話を伺いました。
扇先生
この取り組みの印象はいかがでしたか?
- 普段の授業では触れないような専門性の高い内容を学べる良い機会だと思いました。
特に、法律に関してはテーマが難しく、子どもたちが興味を示すか不安でしたが、私の心配をよそに、皆しっかりと学びを進めており、感心しました。学生さんたちが、ワークショップやクイズ形式など楽しみながら学べる仕掛けを盛り込んでくれたおかげです。
また、身近な物事を例に出すことで、子どもたちが自分のこととして考えられたのも良かったと思います。
この取り組みを行うことで、SDGsのどの目標達成につなげたいと考えていますか?また、学びを通して、子どもたちに期待することは何ですか?
- 「4.質の高い教育をみんなに」ですね。ただ、今回子どもたちには、この取り組みがSDGsと関係があることを明かしていません。今後、SDGsについて学習する機会があるので、その時にこの取り組みが「4.質の高い教育をみんなに」と関連があったのだと提示しようと思います。今日感じたことや考えたことなど、子どもたち自身の経験の内にあるものと、SDGsという新しく学んだことが頭の中で合致し、自分たちの暮らしにもSDGsがつながっていると実感してくれることを期待しています。
木下先生
取り組みの印象はいかがでしたか?
- 「校舎の窓からいつも見える九州大学。憧れの場所から来た学生さんたちの授業」ということで、子どもたちの学習意欲がいつも以上に高まっていたのを感じました。
また、学生さんたちの笑顔がとても良かったです。子どもたちの様子を気に掛けながら授業を進行し、班の子どもと話す際には子どもと目線の高さを同じにして語りかけるなど、私が大切にしている子どもたちを、同じ地域に暮らす学生さんも大切にしてくれる姿に、胸が熱くなりました。
(写真:子どたちと目線を合わせながら声かけをする学生たち)
九大寺子屋メンバーの声
- 学童保育のボランティアをするなど、子どもとふれあうのが好きでメンバーになりました。今年で5年目ですが、毎回子どもたちの反応がとても面白い。可能な限り続けたいと思っています。
- 小児精神学における発達などについて理解する上で、この取り組みは学ぶところが多いです。また、自分が今まで学んできたことを子どもの教育に生かせる場、地域に還元できる場でもあると感じています。
- 怡土小の子どもたちは人懐っこくて、元気。けれど、真剣に話を聞く時の切り替えもしっかりできていて、授業が行いやすかったです。先生方の日ごろのご指導が行き届いていることがうかがえました。
- 授業づくりで心掛けたのは、自分たちが大学で学んでいることを、どうすれば小学生でもわかるように、また、飽きさせないように伝えることができるかということ。椅子にじっと座っているだけでなく、手を挙げたり、班になったり、体を動かすプログラムを盛り込みました。今後も、子どもたちが興味を持つプログラム、楽しく学ぶ仕掛けに注力し、子どもたちが日ごろ意識していなかったことに目を向け、学ぶって面白いと思ってもらえるように取り組みたいと考えています。
(写真:九大寺子屋メンバー)