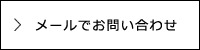トップページ > 市政情報 > 市の計画 > 各分野の計画 > SDGs未来都市 > 令和6年度 SDGs認知・共感促進事業 > 【SDGs認知・共感促進事業】引津小学校の取組を取材しました!
【SDGs認知・共感促進事業】引津小学校の取組を取材しました!
更新日:2025年3月27日
糸島市は令和5年度に「SDGs未来都市」に選定され、「糸島市SDGs未来都市計画」に基づく取組を推進しています。SDGsの達成には、市民・団体・企業など、皆さん一人ひとりの行動が必要不可欠です。
そこで、令和6年度から令和7年度にかけ、「SDGs認知・共感促進事業」を実施することとしています。
市内で活動する市民・団体・企業等のSDGsに関する取組を取材し、情報発信することで、SDGsに関する取組の“認知”と“共感”を促し、SDGsに対する市全体の意識を高め、一人ひとりの行動変容につなげていくことが目的です。
令和6年度は、市内の各小中学校における取組を取材しています。
「SDGsとよく聞くけれど、具体的になにをすればいいの?」と疑問を抱かれている方も、今回発信していく取組を参考に、身近な課題の解決に向けた行動につなげていただければと思います!
- 「SDGs未来都市」選定時のページは、こちら
【引津小学校】海岸清掃・稚魚放流を行い、皆で海の環境を守る
引津小学校は、昭和45年に芥屋小学校と小富士小学校を統合して開校しました。
引津湾や可也山の裾に面した場所に位置し、海と山が近く自然環境に恵まれた学校です。引津小学校の教育目標は「ふるさと引津を愛し、学び合い、深め合い、育み合う子どもの育成」。花いっぱい運動やホウ酸団子作り、校区のお楽しみ会などを通して地域住民と交流を図り、地域とのつながりを深めています。今回は3・4年生が地域のさまざまな団体と協力して行った、幣の浜の海岸清掃と稚魚の放流体験の様子をレポートすると共に、先生と子どもたちの思いや感想をご紹介します。
海の環境問題の現状を知り、関心を高める
令和6年11月5日、幣の浜の海岸清掃と稚魚の放流へ行く前に、3・4年生を対象とした海の環境問題を知るための授業が行われました。環境問題や資源循環をテーマに活動する一般社団法人イドベタの三井さんから、海流の地図を使って、波が多くのごみを海岸に運んでいると説明があり、実際に海に潜って撮影した映像も見せてもらいました。子どもたちはごみが落ちていることで海の生き物が苦しんでいる現状を知り、海の環境問題への理解を深めました。また、海に落ちていたブイ(海面に浮かべて目印に使う浮き)を再利用して作ったスピーカーを見せてもらい、その発想のユニークさに驚きの表情を浮かべていました。
(写真:糸島を拠点に活動する一般社団法人イドベタのみなさん(右側が三井さん))
地域のさまざまな団体と一緒に海岸清掃
子どもたちは芥屋の幣の浜海岸までバスで移動し、糸島ロータリークラブや(一社)イドベタ、引津コミュニティセンター、引津校区振興協議会自然環境部会、糸島市国際交流会の人たちと一緒に海岸清掃を行いました。子どもたちはグループに分かれて作業を開始。ペットボトルやロープ、発泡スチロールなどさまざまなごみが落ちており、中には水中眼鏡を拾い担任の先生に見せに行く子どもの姿も見られました。
「こんなのが落ちていたよ」と担任に知らせる子も
一生懸命にごみを運ぶ子どもたち
子どもたちや地域の人たちが海岸清掃をしていると、近くにいたサーファーも一緒になり清掃活動を手伝っていました。回収したごみの中には韓国語や中国語で表記された容器などもあり、海流に乗って遠くからごみが運ばれてきたことが分かります。サンダルの型抜き後のごみを見つけた(一社)イドベタの三井さんは「これは竜の背中みたいに見えますね」と、廃材アートの材料にするために持ち帰っていました。
(写真:サンダルの型抜き後のごみも廃材アートの材料に)
しゃがんで作業をしている子に何をしているか聞いてみると「マイクロプラスチックを探しています。海にはたくさん落ちていて、魚がエサと間違えて食べてしまうから」と教えてくれました。1時間近くの海岸清掃で、40袋以上のごみが集まりした。
プラスチックの細かな破片もたくさん落ちていた
集めたごみを回収場所まで運ぶ地域の人たち
岐志漁港にてカサゴの稚魚の放流体験
海岸清掃が終わるとバスに乗り、今度は稚魚の放流体験をするため岐志漁港へ向かいました。稚魚の放流は、糸島ロータリークラブの社会奉仕事業「糸島の自然と子どもたちを守り・育てるプロジェクト」の一環で、糸島市内の小学校や保育園などが毎年順番に体験しています。今年は引津小学校と、とまりの森保育園の子どもたちが参加。糸島ロータリークラブ会長の高倉さんが「稚魚の放流を経験して、海の環境を守るという気持ちを持ってもらいたい」と挨拶をしました。
(写真:糸島ロータリークラブ会長の高倉さん)
糸島漁業協同組合の人たちも協力して、カサゴの稚魚3000匹を小さなバケツに分け、子どもたちに配りました。子どもたちは「大きくなってね」「元気いっぱい泳いでね」など口々に声を掛けながら、バケツに入ったカサゴの稚魚を海へそっと放しました。
カサゴの稚魚が入ったバケツ
「大きくなってね」とカサゴの稚魚を海へ放流する子どもたち
最後に、海岸清掃や稚魚の放流に関わった子どもたちと地域の団体のみなさんで一緒に記念撮影をして、今回の活動が終了しました。
(写真:最後は全員で記念撮影)
子どもたちの声
- 自分たちがごみ拾いをしていると、サーフィンをしていた人も一緒にごみを拾ってくれて、うれしかったです。海だけじゃなくて他の所にもゴミが落ちていたら、ごみ箱に捨てに行きたいです。
- ペットボトルのキャップや網がたくさん落ちていたけど、海がきれいになって良かったです。これからもごみは自分で持ち帰って、自分の家で捨てるようにしたいです。
- ごみを拾ってきれいになったから、海に来たいと思う人が増えると思います。海の生き物がプラスチックなどの小さなごみを食べないようにしたいです。
- 稚魚の放流をすると海の中の魚がたくさん増えるのでうれしいです。カサゴの赤ちゃんもかわいかったです。
(写真:「これからもごみ拾いを続けていきたい」と語る子どもたち)
先生インタビュー
3年生担任の柳瀬先生と4年生担任の吉本先生に話を聞きました。
(写真:3年生担任の柳瀬先生(右)と4年生担任の吉本先生(左))
今回の活動のねらいを教えてください。
- 身近な環境の調査や体験を通して、意欲的に課題を追究する。
- 身近な環境問題やSDGsの取り組みに興味を持ち、自分が取り組む課題を決め、計画に沿って行動する。
- ごみ、4R、エネルギー問題、節水、川や水などの自然を守るための学習で学んだことを、分かりやすく工夫して伝える。
このテーマの活動は、どんな背景や問題意識があって行われたのですか?
- 大きなごみは地域の清掃活動などでだいぶ少なくなってきましたが、プラスチックの破片や釣り糸などの小さなごみが落ちていて、鳥が飛べなくなったり、魚が死んでしまったりする現実があります。引津は海が近いので、そこを切り口として地域の方々と一緒に問題意識を持ち、海岸清掃を行いました。
この授業をすることで、SDGsのどんな目標につながり、子どもたちが理解するためにどんな工夫をしましたか?
- 「14.海の豊さを守ろう」につながると思います。3年生では道徳の授業で川の水が汚れて魚が苦しんでいるという内容の学習があり、自分たちの身近な海をきれいにしたいという思いを持っていたので、その思いを今回の活動に生かせるようにしました。3年生での経験をもとに、4年生でさらに学びを深めるという2年の期間をかけ、学習活動を行っています。
実際に活動をやってみて、どんな手応えを感じましたか?
- 給食週間を通して給食の重要性やフードロスの問題に焦点を当て、「2.飢餓をゼロに」につなげられたと思います。また、「1.貧困をなくそう」の面で、給食が提供できる国や地域は貧困率が低いことも、授業を通して伝わったと思います。
給食が子どもたちのところに届けられるまでには、多くの人の努力や苦労、つながりが背景にあることを知り、SDGsの問題を身近に感じてほしいですね。
学びを通して、子どもたちに最も期待することは何ですか。
- まずは、身近な海を大切にしたいという気持ちを持って、生活していける子どもたちになってほしいと思います。SDGsに関心を持ち、身近なところでできることに積極的に取り組んでいってほしいです。