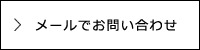トップページ > 市政情報 > 市の計画 > 各分野の計画 > SDGs未来都市 > 令和6年度 SDGs認知・共感促進事業 > 【SDGs認知・共感促進事業】南風小学校の取組を取材しました!
【SDGs認知・共感促進事業】南風小学校の取組を取材しました!
更新日:2025年3月3日
糸島市は令和5年度に「SDGs未来都市」に選定され、「糸島市SDGs未来都市計画」に基づく取組を推進しています。SDGsの達成には、市民・団体・企業など、皆さん一人ひとりの行動が必要不可欠です。
そこで、令和6年度から令和7年度にかけ、「SDGs認知・共感促進事業」を実施することとしています。
市内で活動する市民・団体・企業等のSDGsに関する取組を取材し、情報発信することで、SDGsに関する取組の“認知”と“共感”を促し、SDGsに対する市全体の意識を高め、一人ひとりの行動変容につなげていくことが目的です。
令和6年度は、市内の各小中学校における取組を取材しています。
「SDGsとよく聞くけれど、具体的になにをすればいいの?」と疑問を抱かれている方も、今回発信していく取組を参考に、身近な課題の解決に向けた行動につなげていただければと思います!
- 「SDGs未来都市」選定時のページは、こちら
【南風小学校】日頃の感謝を込めて、野菜の生産者を招いた「給食感謝の会」
南風台・美咲が丘の2つの大きな宅地開発によってできた南風校区。地域と学校が連携した行事が活発に行われており、地域文化祭や音楽祭、ふれあい夏祭り、スポーツin南風などの行事に地域住民が積極的に参加しています。
「志をたて 自ら考え行動し 他者と共にたくましく生きる 自己肯定感の高い南風の子の育成」という教育目標のもと、子どもたち自身が考えて行動する学びや活動が授業に取り入れられています。例えば学活や総合、社会科の時間に「校区探検を行い、バリアフリーがどれだけ取り入れられているかを調べる」「校区の公園に行き、ゴミ拾いを行いながら量と種類を調べる」など、地域に根差した授業は、SDGsの目標達成にもつながる内容です。
今回、「学校給食記念日」にあわせて行われた「給食とSDGsの学習」と「給食感謝の会」を訪ねました。
児童会「南風朝の会」で給食の歴史を知る
2024年12月18日。しんと静まり返った放送室。マイクを通して6年生男子児童の第一声が響きます。
「これから南風朝の会を始めます」。今日の1時間目は定期的に行われている児童会です。1階の放送室に少し緊張した面持ちで集まったのは、放送委員会と給食委員会の子どもたち。5、6年生約20名がそれぞれの原稿を手に、会の進行を見守ります。順番にマイクの前に立ち、ハキハキとした声で給食の成り立ちと歴史を紹介していきます。
日本で最初に提供された給食の献立、戦争で一時中断された歴史、再開した日が「給食記念日」に設定されたこと。子ども達のわかりやすい説明と初めて知る内容に思わず聞き入ります。その後は、給食に関するクイズなど楽しい内容が続きます。段取り良く会は進行し、最後に給食感謝の会で渡されるプレゼントが紹介されました。
放送室。順番に原稿を読んでいく
生産者と調理員へ渡すカレンダー
給食委員が集合。「クイズが盛り上がった!」とうれしそうだった
給食とSDGsのつながりと
続く2時間目は、5年生の「学活」へ。給食記念週間に関する学習で、めあては「給食とSDGsの関わりを見つけ、給食があることの良さについて話し合おう」です。導入は「給食について知っていることは?」という答えやすい問いかけから始まりました。子どもたちが毎日食べている給食の特徴を発表し、先生が皆の意見をまとめていきます。
(写真:給食がどんなものか意見を出し合う)
続いて、SDGsを子どもにも理解しやすく説明した動画を視聴。どの達成目標と給食が結びついているのかについてループで話し合います。
(写真:スライドを使ったSDGsの説明)
意見がまとまったところで発表です。子どもたちから、さまざまな意見が飛び出しました。
- 給食は同じ献立を皆が平等に食べるから、「10.人や国の不平等をなくそう」につながる。
- 栄養バランスの良い給食を食べることで元気になれるから、「3.すべての人に健康と福祉を」につながる。
- 給食を残さないことはフードロスを減らすから、「12.つくる責任、つかう責任」につながる。
- 牛乳パックの回収は「13.気候変動に具体的な対策を」につながる
友だちと自由に意見を交換
給食とSDGsに関する活発な意見をまとめて終了
子どもたちの柔軟な発想を聞いていると、食に直結する「1.貧困をなくそう」「2.飢餓をゼロに」に限らず、多くの達成目標につながることに気づかされます。
最後は「給食を食べることは、自分たちにとってどんな良さがあるのか」「これから自分が大切にしていきたいこと」をまとめて、2時間目終了のチャイムがなりました。
給食感謝の会
いよいよお待ちかねの給食の時間になりました。本日のメニューは、トマトの豆乳クリームスパゲティ、ゆで野菜サラダ、ミルクパンなどです。配膳を終えたところで、各クラス代表の子どもたちが校長室へゲストをお迎えに行きます。ゲストは南風小学校に野菜を納品している生産者です。野菜を納品している生産者8名中、今回は4名が来校されました。
1年1組の教室。きゅうりやなすを納品されている寺田さん
3年3組の教室。三坂さんの作ったキャベツが今日のサラダに使われていた
5年1組の教室。人参や大根を納品されている平野さんと

玉ねぎや小松菜を作られている土井さんと、しりとりで盛り上がる6年3組の子どもたち
各クラスに到着した生産者は、子どもたちに拍手で歓迎され、名前を紹介されて子どもたちの輪の中へ入りました。さらに、いつもお世話になっている給食調理員、クラス担任以外の先生たちも各クラスに招待しました。おいしい給食を味わいながら、クラスごとに企画したクイズやゲーム、質問タイムなどを行い、感謝の会がにぎやかに進みます。食べ終わった頃、手作りのカレンダーや感謝のお手紙をゲストにプレゼントしました。
最後は手を合わせて、精一杯の感謝を込めて「ごちそうさまでした!」と元気にあいさつしました。

(写真:生産者の平野さんを囲んでポーズ)
子どもたちの声
給食記念週間に関連した取り組みを通じて、給食の歴史やSDGsについて学んだ子どもたち。6年生に感じたことや考えたことを聞いてみました。
- 給食は明治22年から始まって、時代ごとに豪華になっていき、今の給食があるんだとわかりました。これからは給食を作ってくれた人と昔の給食を作った人にも感謝しながら、毎日完食したいです。好き嫌いをしないように食べていきたいです。
- 給食には明治時代から今日までいろいろな人の思いがこもっていて、これからもおいしく食べてもらうために進化していることを知りました。そんな給食は日本の宝だと思います。給食を残さずに食べることで、これからも歴史が受け継がれていくと思います。
- 給食の良いところは、家では食べられないメニューが出るところと友達みんなと楽しく食べることができるところです。給食は栄養バランスをしっかり考えて作ってくれているので、生産者や調理員のみなさんに感謝して食べたいと思いました。給食で栄養が取れるし、温かいものを食べることができ、お弁当を作る保護者の負担も減ると思います。

(写真:6年生の子どもたち。一番人気の献立を聞くと揚げパンと教えてくれた)
先生インタビュー
栄養教諭の梅野先生にお話を聞きました。

(写真:梅野先生は、日頃から子どもたちに好きな献立を聞くなどコミュニケーションを心がけているという)
今回の授業を含め、どのような実施計画になっていますか。
- 12月24日は、日本で学校給食が最初に始まった日を記念した「学校給食記念日」です。本校ではこの日にあわせて、1週間の「給食記念週間」を設定しています。
学活の時間を利用して、給食ができるまでに関わっている人の苦労、給食の歴史、世界の食糧事情などを学習していきます。また、今回のように生産者さんをお招きして一緒に給食を食べ、子どもたちと交流する機会を設けています。10月末から各クラスで話し合いをして、生産者さんや調理員さんへのプレゼントを考えて準備しました。
今回はコロナ禍を経て、5年ぶりに生産者さんをご招待できました。再開できてうれしいです。
今回の授業(活動)の目的・ねらいを教えてください。
- 大きなねらいは給食に関心を持ってもらうことです。給食ができるまでにどのような人が関わっているのかを知ってもらうことが目的です。苦手な野菜があっても、それを作っている人の苦労を知り、実際に話を聞くことで、「食べてみようかな」と思うきっかけになればと思っています。
また、給食の歴史や背景を知ることで、給食を食べることができるということが、決して当たり前ではないと感じてほしいと思います
この授業を通して、SDGsのどんな目標達成につなげたいと考えていますか。
- 給食週間を通して給食の重要性やフードロスの問題に焦点を当て、「2.飢餓をゼロに」につなげられたと思います。また、「1.貧困をなくそう」の面で、給食が提供できる国や地域は貧困率が低いことも、授業を通して伝わったと思います。
給食が子どもたちのところに届けられるまでには、多くの人の努力や苦労、つながりが背景にあることを知り、SDGsの問題を身近に感じてほしいですね。
学びを通して、子どもたちに最も期待することは何ですか。
- 栄養教諭として一番望むのは、なるべく食べ残しをしないでほしいということです。苦手な食材を無理に食べるのではなく、自分が食べられる量を器に盛る、食わず嫌いのものに興味を持って挑戦してみる、給食週間がそんなきっかけになるとうれしいです。こうした学びを通して食べ物を大事にするという気持ちを育んでいきたいと思います。
この授業以降、SDGsの取り組みはどのように展開する予定ですか。
- 本校では、残食を減らすために「リクエスト給食」という取り組みも行っています。クラスで給食を完食した日にはシールをつけ、目標を達成すると賞状を渡します。100回達成すると給食の献立を1品リクエストできるというものです。
クラスの食缶が空になれば完食達成となりますので、無理に食べるというわけではなく、食べることができる子、食べたい子が率先して食べるスタイルです。
年間190回程度の給食を提供していて、道のりはなかなか大変ですが、12月時点で4クラスが達成しています。
これからも食の楽しさと大切さを伝えて、関わる人たちに感謝して食べる心を育てていきたいと思います。