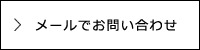トップページ > 市政情報 > 市の計画 > 各分野の計画 > SDGs未来都市 > 令和6年度 SDGs認知・共感促進事業 > 【SDGs認知・共感促進事業】一貴山小学校の取組を取材しました!
【SDGs認知・共感促進事業】一貴山小学校の取組を取材しました!
更新日:2025年2月20日
糸島市は令和5年度に「SDGs未来都市」に選定され、「糸島市SDGs未来都市計画」に基づく取組を推進しています。SDGsの達成には、市民・団体・企業など、皆さん一人ひとりの行動が必要不可欠です。
そこで、令和6年度から令和7年度にかけ、「SDGs認知・共感促進事業」を実施することとしています。
市内で活動する市民・団体・企業等のSDGsに関する取組を取材し、情報発信することで、SDGsに関する取組の“認知”と“共感”を促し、SDGsに対する市全体の意識を高め、一人ひとりの行動変容につなげていくことが目的です。
令和6年度は、市内の各小中学校における取組を取材しています。
「SDGsとよく聞くけれど、具体的になにをすればいいの?」と疑問を抱かれている方も、今回発信していく取組を参考に、身近な課題の解決に向けた行動につなげていただければと思います!
- 「SDGs未来都市」選定時のページは、こちら
【一貴山小学校】地域の人に見守られ、長い道のりを毎日歩いて登校
のどかな田園風景が広がる一貴山は、田んぼ脇の草花や小さな生き物たちが、季節の移ろいを教えてくれる自然豊かな地域です。

一貴山小学校の子どもたちは、見晴らしのいい田んぼ脇の通学路を毎日歩いて登校します。平均して1.5km~2kmの道のりを、30分~1時間かけて歩いて来る子どもたち。
SDGsの目標のうち「3.すべての人に健康と福祉を」「11.住み続けられるまちづくりを」に関連して、長距離を歩いて登校することで丈夫な体、人への思いやりや自立心、地域の人とのつながりなどが育まれています。
先生と子ども、保護者や見守り隊の人に、歩いて登校することについて聞きました。
(写真:子どもたちは見守り隊や保護者に見守られて登校)
山々と見渡す限りの田園風景が広がる通学路
「おはようございます」、脊振の山々から昇る朝日を体いっぱいに浴びた子どもたちが、次々と一貴山小学校に登校して校長先生に挨拶をします。
校長先生は朝8時前には正門に立ち、「おはよう!」と笑顔で子どもたちを迎え入れます。どのような天候の日でも学校までの長い道のりを歩いて登校する子どもたちは、学校に着くと一目散に運動場に出て、始業の時間までサッカーなどの外遊びをするほど元気いっぱいです。
(写真:山の稜線から太陽が顔を出す壮大な景色)
一貴山小学校の周辺は、見晴らしの良い田園風景が一面に広がっています。小学校の正門から真っ直ぐ伸びる通学路は、両側が田んぼで、風が吹いても遮るものが何もありません。
(写真:遮るものが何もない直線道路)
太陽の光が朝露をキラキラと照らす美しい景色を望める反面、山から吹き下ろす冷たい風が、霜の降りた田畑を通り抜け、登校中の子どもたちに容赦なく吹き付けます。
夏は日陰もないので、ギラギラの直射日光と道路の輻射熱を浴びて登校しなければいけません。
雨にも、風にも、雪にも負けない子どもたち
学校まで1時間ほどかかる道のりを、毎朝子どもたちに付き添って一緒に歩くのは、登校中の安全を見守る「いきさん見守り隊」のメンバーや、ボランティアの保護者たちです。
道中のケガや体調不良、集団行動の中で起こりがちな子ども同士のトラブルにも臨機応変に対応しています。
暴風や強風の日は、小さな低学年の子どもが風に吹き飛ばされそうになるので、1列になって前の子どものランドセルの端をしっかり持ち、みんなで列車のようにつながって歩きます。常に見守り隊が声を掛け、子どもたちの安全に注意を払います。

風に飛ばされないように列車のようにつながって歩く

冷たい風が吹きすさぶ日も辛抱強く歩く
突然の雨で傘を忘れた子がいれば、仲良く相合傘で登校するのは当たり前。
雪が積もれば転ばないように支え合ったり、身を寄せ合って寒さをしのいだり。時にはみんなで大合唱をしながら寒さを吹き飛ばし、毎日元気に助け合いながら歩いています。
道を譲ってくれた車には、横断歩道を渡りきったところで振り返り、運転手さんに深く頭を下げてお礼を言います。上級生が下級生のお手本となり、その姿勢は自然と子どもたちに引き継がれ、身に付いていくそうです。
思いやりも感性も、一貴山の人と自然が教えてくれる
毎日一貴山の自然に触れながら登下校する子どもたちは、自然に対する感性も豊かに育っています。
季節の移り変わりや、空の変化、雲の形について話したり、虫や小さな生き物を観察したり、四季折々の草花を摘んで遊びます。
虫かごを持って登校してもいいので、途中でトカゲを捕まえて学校に連れて行く子もいるそうです。

(写真:大きな虹にみんな大興奮)
「霜の中に生えたツクシなど、小さな春を見つけることも、子どもたちはとても得意」とボランティアの保護者は話します。
「今日はこんなことがあったよ」と、子どもたちの通学途中の様子を他の保護者に伝えています。親に安心感を与えるだけではなく、子どもたちがその日感動したこと、楽しかったことを親子で分かち合えるようにとの思いからです。
毎日一緒に歩く仲間たち

来年1年生になる未就学児の手をつないで歩く
1年生になったばかりの子どものランドセルや荷物を上級生が持ってあげたり、未就学児の手を取って登校練習に付き添ったり、そんな上級生の姿に憧れを抱く子もいるようです。
転んでケガをした子に、その場で手当てをする見守り隊や保護者の愛情にも包まれて、子どもたちは互いに助け合い励まし合って登校します。日々の登校で、友達への思いやりや信頼が、一歩一歩しっかりと育まれています。
子どもたちの声
毎日歩いて登校する子どもたちは、年に3回(7、12、3月)学校から表彰されます。担任の先生が毎朝の健康観察で歩いてきた子どもを確認し、養護教諭が対象児童の名簿をもとに賞状を作成します。
朝の会で教頭先生から賞状が渡される様子
賞状を手に笑顔の2年生の子どもたち
歩いて登校して良かったこと、大変なことはありますか。
- 他の学年の人と歩きながら話ができることです。
- 運動になるし、ガソリンの節約になって家計にもやさしいと思います。
- 寒いときと暑いときが大変です。
登下校時の楽しみや発見したことはありますか。
- 人との会話です。
- 季節の移り変わりを感じて、気候の変化にも敏感になりました。
見守り隊の人との思い出やエピソードを教えてください。
- 見守り隊の人から挨拶をしてもらってうれしいです。
- けがをしたときに対応してもらえるので安心です。
- 1年生のお世話をすることは大変なので助かります。
- 昔の話をしてもらえるので、勉強になります。
一貴山のどのようなところが好きですか。
- 自然が豊かなところです。
- 人が少ないのでつながりが深くなると思います。
地域のためにやってみたいと思うことはありますか。
- あいさつ運動、環境美化、スタンプラリーをして地域のことを知りたいです。
見守り隊の人たちへメッセージ
- いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします!
先生インタビュー

(写真:2年生担任の永末先生)
どんな背景や問題意識があって「歩いて登校」を推奨することになったのでしょうか。
- 保護者による送り迎えが増えていたため、学校で歩くことを奨励する取り組み(歩いて一貴山賞)が生まれました。次いで、見守り隊が生まれ、地域と連携して歩いて登校することを奨励する取り組みへと発展しました。
歩いて登校する子どもたちを見て、普段感じることや気付きはありますか。
- 異学年間の交流があり、子どもたちはお互いをよく知っていると感じます。昼休みには、2年生から6年生までが仲よくサッカーをして楽しんでいる様子が見られます。
「歩いて登校」には基礎体力の向上と自立心がねらいとありますが、自立心を具体的に教えてください。
- 高学年は班長や副班長として、低中学年のお世話やその手本としてのふるまいを意識するようになります。また、自分自身が低学年の頃に受けたお世話を他者にすることで、自分自身の成長に気づき、高学年らしい自立心が育っています。
歩いて登校する取り組みとSDGs目標の結びつきを子どもたちが理解するために、どのような工夫をしましたか。
- 「11.住み続けるまちづくりを」に関して、見守ってくださる見守り隊のみなさんへの感謝の会を2月に開くことで、お互いに支えあうことの大切さを理解させています。
「3.すべての人に健康と福祉を」に関しては、特に理解させるための工夫はしていませんが、6年生は健康面での充実を感じているようです。
歩いて登校する取り組みで、今後SDGsに結びつけてやってみたいことはありますか。
- 登下校時に自動車を使用する場合のCO2の排出量について、算出してみようと思っています。
地域の人インタビュー
20年近く一貴山小の子どもたちの見守りを続けている伊藤さんと西尾さんに、活動についての思いを聞きました。
(写真:いきさん見守り隊の西尾さん(左)と伊藤さん(右))
いきさん見守り隊について教えてください。
- 見守り隊の登録をしているのは現在50名ほどです。毎朝メンバーが日替わりで登校中の見守り活動をしています。
特定の場所に待機して見守る人もいれば、子どもたちと一緒に学校まで歩いて見守る人もいます。私たちは学校に来て、始業まで子どもたちと一緒に校庭でサッカーなどをして遊びます。もう15年から20年、毎朝子どもたちを見守り続けてきました。
子どもたちとの関わりの中で、大切にしていることはなんですか。
- 見守り隊では常に3つのことを考えて活動しています。
1.子どもが事故や犯罪などに巻き込まれないように安全面に留意すること、
2.集団行動ができるようにサポートすること、
3.登校中にいじめなどがないかに気を配ること。
また、日本ユニセフ協会の「子どもの権利条約」にならい、子どもの権利を尊重して接することを心掛けています。
(写真:教室に戻る子どもたち一人一人に声を掛ける見守り隊)
見守り隊の役割について思うことを教えてください。
- 子どもには大人の目が必要だと思います。毎朝一緒に登校して、子どもたちを見ているから気付くこと、分かることがあります。
子どもたちと関わりながら、普段と様子が違えば「どうしたの」と声を掛けます。一緒に遊ぶ中で、先生や親にも言えずにいたことを、ほろっとこぼすこともあって…。
そんなときは子どもの心を受け止めて、しっかり話を聞いてあげます。何かあれば解決できるように手助けをして、温かく見守ることが自分たちにできる役割だと思っています。
地域の人たちに伝えたいことはありますか。
- とにかく遠くからでも、農作業中でも、家の中からでも、子どもたちの登下校の安全を見守ってあげてほしいです。
子どもだけではなく、地域の高齢者など、お互い声を掛け合って、気軽に挨拶して、みんなで連携して地域を見守る。その姿勢が子どもたちにも伝わって、将来見守り隊になってくれる子が出てきたらうれしいです。