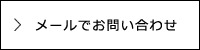トップページ > くらしの情報 > 住宅(耐震等)・市営住宅 > 市営住宅のご案内
市営住宅のご案内
更新日:令和6年10月1日
令和6年度 市営住宅の入居者募集について
●募集期間 令和6年10月15日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
(申込書配布場所;市役所1階総合案内、市役所3階都市施設課)
●受付時間 8時30分から17時15分まで ¶ただし、土曜日・日曜日は除きます。
●受付場所 糸島市役所 3階 都市施設課 住宅係(6番窓口)
●申込方法 持参、または郵送( 郵送の場合は10月31日の消印有効 )
●申込資格 1、糸島市内に住民登録または勤務場所がある人
2、原則として、同居しようとする親族がいる人
3、世帯の収入月額が158,000円以下であること(老人世帯や障がいのある人などが
おられる世帯は214,000円以下)
4、住宅に困っている人
5、暴力団員でない人
6、地方税の滞納がない人
●入居時期 令和7年2月以降
●入居者選考 入居申込者が募集戸数を超える場合は、公開抽選を行い、入居者を決定します。
●抽選会 日時 令和6年11月11日(月曜日)14時開始
会場 市役所1階101号会議室
抽選会にて、入居者と入居補欠者を決定します。決定後、入居者と入居補欠者
には通知をします。
〇募集する部屋はこちら↓
令和6年度募集団地一覧
市営住宅とは
「公営住宅法」に基づき、糸島市が、国や県の補助を受け建設した賃貸住宅です。
入居者の募集
糸島市は、市営住宅の入居者の募集は、年1回行っています。例年、10月ごろ募集要項を配布し、翌年2月ごろに入居いただくスケジュールとしています。ただし、住宅の空きがない場合には募集は行いません。また、応募多数の場合には抽選により入居者を決定します。
募集要項の配布時期は、広報いとしま及び糸島市ホームページでお知らせします。
募集要項では、募集する団地の名称・間取り等をお知らせします。
入居決定者には、後日、住宅の内覧会を実施します。
市営住宅は住宅に困窮する低所得者を対象にした公共施設です
市営住宅は、公営住宅法に基づき、糸島市が住宅に困窮する低所得者に対し、安い使用料でお貸ししている住宅です。
下記の困窮理由に該当する人が利用することができます。
また、市営住宅の入居者は、自分が入居する部屋のみでなく、住宅敷地や共有スペース・共同設備について、住宅の日常的な管理(清掃、除草、修繕など)は、入居者自身で行っていただきます。
住宅内には、照明器具やガスコンロ、エアコン、カーテン等の設備はありません。また、前入居者の退去後、不良箇所の修繕は行っていますが、生活に支障のない範囲の傷みや汚れなどは受忍していただいています。
同様に退去時には、入居期間に関わらず、次に入居される人のための「畳の表替え」と「襖の張替え」は、必ず行っていただきます。
公営住宅の目的
公営住宅法(昭和26年法律第193号)第1条抜粋
公営住宅(市営住宅を含む)は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、国民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
市営住宅では、共用部は入居者での自主管理となります
市営住宅は、低廉な家賃で賃貸していますので、入居者様からの使用料だけでなく、市民の皆さまから納められた税金も住宅の運営費用となっています。
民間の賃貸住宅では、家賃のほかに管理費等を徴収して、これらの管理を代行している場合がありますが、市営住宅では入居者自身がこれらの管理を担うこととし、管理費の徴収を行っていません。
入居者の保管義務等
公営住宅法第27条抜粋
公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
入居者は「地域の一員」です
市営住宅は「住居」であり、入居者は「地域住民」です。このため、周辺の世帯住民と同じく、地域活動や環境整備活動などへの参加・協力が求められます。
さらに、棟・団地が1つのコミュニティ(社会共同体)です。このため「入居者同士の理解・協力・協調」が必要不可欠です。「使用料さえ納めればいい」という考え方では、他の入居者に迷惑をかけることもありますので、ご留意ください。
入居者は、各種届出や手続きが必要です
市営住宅の入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させる場合や室内の模様替えを行う場合、15日以上住居を使用しない場合等は、市への届出や承認が必要な場合があります。
また、収入額等により、翌年度の住宅使用料が変動するため、毎年、収入申告書の提出が必要となります。
入居申込みができる人
- 市内に住所又は勤務場所を有する人であること
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
- 世帯の月額収入 158,000円以下で(老人世帯や障がいのある人などがおられる世帯は214,000円以下)あること。
- 現在、住宅に困窮していること。(下記困窮理由参照)
- 入居予定者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 地方税を滞納していないこと。
困窮理由
以下のいずれかの理由に該当する人(単身入居の条件)
上記「入居申込みができる人」の1から3と5から6を備え、下記のAまたはBに該当する人。-
- 60歳以上の人で配偶者がいない人
- 60歳未満の人で、下記要件のうちいずれか1つを満たしている人で配偶者がいない人。(離婚手続き中の人を含む。)
- 障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者でその障害の程度がアからウまでに掲げる障害の種類に応じそれぞれアからウまでに定める程度であるもの
ア 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障がい(知的障がいを除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障がい イに規定する精神障害の程度に相当する程度
- 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
- 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でア又はイのいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの