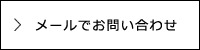トップページ > 市政情報 > 広報・広聴 > 市長への手紙 > 令和7年掲載分 > 「市長への手紙」に寄せられたご意見と回答(令和7年9月受付 掲載希望分)
「市長への手紙」に寄せられたご意見と回答(令和7年9月受付 掲載希望分)
更新日:2025年10月31日
水源地等の売却に係る規制ついて
私は、糸島市二丈の土地が売りに出されていることを知りました。この土地の所在地、そしてその性質を考えますと、市民生活のみならず将来にわたる公共の財産として、慎重に扱うべき案件であると確信しております。
役場の都市計画課のお話として、「売りに出されていることは仕方がない」とのご返答をお受けしましたが、私はそれでは済まされないと思います。なぜなら、同様のケースで 取り返すための制度や条例改正を重ねてきた自治体が既に存在するからです。
以下に事実とエビデンスを整理し、お願いと提案を含めて申し上げます。
事実と根拠
1. 熊本市の事例
- 最近、熊本市では水源地の土地が外国資本に取得される事例が報じられています。熊本市は地下水を水道水の100%に使う数少ない都市であり、水源の涵養や保全が市民の生命・安全に直結しています。
- このような事態を受けて、熊本市では「地下水保全条例」の制定や、揚水量の報告義務、涵養活動(雨水浸透など自然に水を保つ森林・土地利用の管理)の強化を進めており、住民の信頼回復・公共利益の保護に向けた制度整備の例となっております。
2. 日本全国の動向
- 林野庁の調査によれば、外国人・外国法人による森林の取得は近年増加しており、2006年~2023年で 358件、2,868ヘクタール に及んでいます。用途が必ずしも水源のみではなくても、水源涵養機能を持つ土地が関わるケースも含まれています。
- 現行法制度(森林法・所有者届出制度・重要土地利用規制法など)では、「所有」を把握する制度は整備されつつありますが、「利用」「保全」「用途変更」に関する予防的な規制や、公共性を持つ水源地を明確に守る枠組みは十分とは言えない、という指摘があります。
3. 福岡県・保安林制度
- 福岡県には「保安林制度」があり、その中の「水源かん養保安林」は、水源地域の森林が雨を蓄え、河川流量の安定化、洪水や渇水の緩和、そしてきれいな水を育む効果を持つものとされています。
- 保安林に指定されれば、立木伐採・土地の形質変更などに制限がかかり、森林を守る制度的な枠があります。これを活用することが可能です。
なぜこの土地の保全が重要か
この土地が今後何らかの目的に転用されたり、所有が変わることで、水質や水量への影響が生じる可能性がある。特に豪雨・集中降雨や渇水の増加が懸念される現在、「安定した水の供給」「安全な生活環境」「生態系の保全」という点で、今ある自然を守る責任は非常に重い。
また、市民の信頼、安心を得ることは行政の使命であり、防災・環境保全・住民福祉の観点から、このような土地の保全は長期的な行政コスト削減にも繋がる(例えば、水源の汚染や減少が起これば浄水処理等でのコストが上がる)。
未来を創るとは、ただ経済成長を追うことではなく、次の世代に「水」「自然」「暮らしの安全」をきちんと引き継ぐことだと思います。
以上からお願いです。
市長に以下のことを強くお願い致します。
1. この土地の売却について見直しを行ってください。
特に、水源地を含むことを理由に、市や福岡県の保安林制度、あるいは他の環境保全条例を適用できないか検討してください。
2. 地下水保全条例などの制定を視野に入れてください。
熊本市などのように、「揚水量の報告義務」「用途変更や土地利用の変更に際する事前審査」「涵養活動の義務化」などを含む条例を整備することで、水源を守る制度的な防波堤を作ってください。
3. 地域住民の意見を聴く場を設けてください。
このような土地の重要性を市民が理解し、行政と共に守るという共感があれば、協力も可能です。公開の説明会や意見募集の場を早急に設けていただきたい。
4. 土地の所有・用途・取引の情報の透明性を確保してください。
今、誰がどういう条件で取得しようとしているのか、その用途は何か、市民が知る権利があります。
未来は、今をどう守るかによって築かれるものです。もし私たちが、かけがえのない水源地を「後から気づいて守ろう」としても、それが可能でなくなる時が来るかもしれません。
どうか、市長として、糸島市の「自然、水、暮らしの安全」を守る立場を取ってください。この土地について、「仕方がない」という態度ではなく、「どう守るか」「どう未来に責任を持つか」を、ぜひとも率先して示していただきたいと思います。
回答要旨
(1)、(4)について
水源地を含む土地が適切に守られるべきと心配されている点、また、その保全の必要性について多くの方が関心を持たれていることについては承知しております。
一方で、現在の法制度においては、外国人を含む民間事業者等による土地の取得について、原則として制限する法律はなく、都市計画法においても土地の売買そのものを制限することはできません。また、森林法においては、保安林の伐採や土地の形質変更等の制限はありますが、土地の売買を禁止する制限はありません。なお、ご投稿の土地については、現時点で保安林に指定されていません。
土地の取引の把握についても、安全保障上重要な施設の周辺など、国が指定した区域の土地取引を把握する仕組みや、一定規模以上の土地の取引があった際に届け出る制度はありますが、すべての土地の取引を把握することができる法制度もありません。
現在、国会や政府に対し、国土保全と安全保障の観点から外国資本による土地売買を規制し、適切な管理体制を構築するための法整備を求める意見書が提出されるなど、国レベルでの対策が求められていますが、現時点で市が民間同士の全ての土地取引を把握し、また規制することはできないのが現状ですのでご理解ください。
なお、『「売りに出されていることは仕方がない」と返答を受けた』とのことですが、実際には、市として民間同士の土地取引を把握していないこと、また都市計画法によって土地の売買を制限することはできない旨を説明したものであり、そのようにご理解いただけますと幸いです。
(2)、(3)について
現時点において、当該土地による水源への影響は限りなく低いと見込まれることから、地下水保全条例の制定予定はありません。なお、この土地に限らず、大規模な造成や開発行為等については、都市計画法や宅地造成及び特定盛土等規制法をはじめとする関係法令等の順守を徹底するとともに、必要に応じて、地域との協定締結や住民説明会等の実施を依頼するなどし、市でも引き続き状況を注視してまいります。