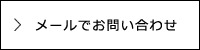トップページ > 市政情報 > 広報・広聴 > 市長への手紙 > 令和6年掲載分 > 「市長への手紙」に寄せられたご意見と回答(令和6年3月受付 掲載希望分)
「市長への手紙」に寄せられたご意見と回答(令和6年3月受付 掲載希望分)
更新日:2024年5月21日
保育料について
現在、子ども3人を育てています。
3人目の3才未満の子どもを保育園に預けたいと思っても、空きはなく、認可外だと3人目でも全額負担になります。
認可だろうが認可外だろうが、子どもを預け働くために保育園があるのに、認可外だと補助がないのは大変困ります。
福岡市では認可外もファミサポも2人目から補助が出ると聞きました。
昔市役所に子育ての件で補助などないのか尋ねた際に財源がないと言われましたが、兄弟児を産み育てる環境がないことに、少子化の拍車がかかる一つの要因があるのではないでしょうか?
また、出産によって退職する女性も多くいる中で、2026年度から始まる誰でも通園制度は実現したら有り難いですが、これも認可保育所にとどまることなく、認可、認可外、ファミサポ、ベビーシッター、など多様に選べることで、様々な家庭の親子に福祉の目が行き届くようになると思います。
糸島市に今後の子育て環境の改善を求めます。
回答要旨
本市の0歳から2歳までの保育所等利用料については、市民税の所得割額や子どもの人数など、一定の要件に応じて第二子以降の減額を行っており、この減額措置は国の幼児教育・保育の無償化制度に基づき実施しているものです。
お手紙にありましたように、認可と認可外により生じる保育料の減額措置の有無などで不公平感を抱かれることについては、市としても理解をしており、また、福岡市の事例も承知しております。
市としましては、こどもの健やかな成長を社会全体で後押しするための施策などは、財源の大きい小さいによる地域格差や市町村間での競争が起きないよう国の政策として実施されるべきものであると考えます。そのため、本市では全国市長会等を通じ、国に対して制度拡充の要望を続けています。
したがいまして、認可外保育施設における0歳から2歳までの保育料減額化については、国の基準以上に自治体独自の減額措置を行うこととなり、相応の財政負担が生じますので、市単独で実施することは十分な検討が必要であり、現時点では実施の予定はございません。
なお、認可保育所の空き枠不足への対応については、令和7年4月に、民間の認可保育所を新設し、新たに80人分の受け皿を確保する予定です。
また、こども誰でも通園制度につきましては、ご案内のとおり、現在、国において、本格実施を見据えた試行的取組が展開されており、本市においても、その結果を踏まえた取組が推進できるよう、関係施設と協働しながら準備を進めていくこととしております。
子育て施策の充実に当たっては、国の少子化対策の動向を注視するとともに、市民の皆様のご意見を踏まえながら、経済的な面だけでなく、社会全体で子育て世帯を支えるための施策、事業の拡充に努めてまいりますので、どうぞご理解の程よろしくお願いします。
糸島市の魅力について
糸島市の魅力について教えてください。
ちなみに自然や土地柄といったもの以外でお願いします。
というのも社会人になって住んでみて、まったくと言っていいほど糸島の魅力(行政のやったこと)がわかりません。
市役所含め公務員の方は非常に勤勉に働かれているとは思っていますが、私が馬鹿なのかいまいち良い市だなと思えないんです。
糸島市は他の市町村と比べ、ここは全く負けてないや、ここは一番ですといったものはあるのでしょうか?
この市に住んで良かった、もっとみんなに選んで住んでほしいと思える市になってほしいです。
回答要旨
自然や土地柄を除く糸島市の魅力は何かといったお問い合わせについて、市民のみなさまそれぞれが感じる魅力はさまざまであり、糸島に住んでよかったと思っていただける要素もさまざまだと認識していますが、本市の代表的な魅力と捉えている事項については以下のとおりです。
1.豊かな自然環境を生かした都市近郊型の農業や畜産業、水産業が盛んであり、新鮮な農林水産物が存在すること
2.福岡市という大消費圏に隣接しており、交通利便性や都市的利便性を兼ね備えていること
3.移住者の増加に見られるように、仕事と余暇を両立できる住環境があること
4.九州大学が存在し、その知的資源を行政課題・地域課題の解決につなげることができること
今後とも、市民のみなさまに住んでよかった、住み続けたいと思っていただけるようなまちづくりに取り組んでまいりますので、本市のまちづくりに対し、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
公園樹木の伐採について
高田東公園のシンボルだった大きな木(銀杏か桜か不明ですが)が、枝はともかく、もともとあったサイズの半分ほどまで伐採されており、緑が全く無い状態になっていました。
近隣住宅への配慮も必要かと思いますが、ある程度公園や街の景観を保つことも必要かと思います。あれは誰が見ても酷すぎる伐採かと思います。もう少し考えてほしいです。
回答要旨
ご指摘の高田東公園の樹木については、樹高が高くなっており、行政区において倒木の危険性を危惧されていました。市としても、近隣への被害の可能性があり剪定が必要と判断したことから、地元行政区とご相談しながら樹木の剪定を実施しました。
剪定した樹木は、クスノキという樹種になりますが、クスノキは成長速度がとても速く、翌年度には枝葉を付け、数年で数メーター成長することが一般的です。
そのような特徴を踏まえ、行政区、樹木剪定業者、市で、今後の樹木の大きさや見栄えも検討した結果、強剪定と言われる方法により剪定を実施しています。
今年の初夏の頃には芽吹き、数年後には枝葉を付け、一回り小さい樹木に成長する予定ですので、どうぞご理解いただきますようお願いいたします。
牡蠣小屋へ向かうバスについて
糸島市民ではなく福岡市民です。
住民以外が意見を伝える場が分からずこちらで失礼いたします。
私は牡蠣が大好きで、毎年シーズンになると月2回は糸島の牡蠣小屋にお邪魔しております。
私も連れも酒を飲みますので、筑前前原駅まで電車、駅からはバスを乗り継いで牡蠣小屋へ向かうのですが
毎年、駅からどのバスに乗ればいいのか迷います。
小さいコミュニティバスが多いですが、土地勘のない者には行先や経由地が分かりづらいのです。
牡蠣シーズンの土日には駅前のバス停に行列ができていますが、バスが来るたびに並ぶ人が「これ乗ったらいいの?」「どれに乗ればいいの?」と戸惑っておられたり、運転手さんに尋ねたりする様子が多く見られます。
そこで、バス停に「この漁港に行くにはこのバスに乗る」と分かりやすく掲示していただけないでしょうか。
糸島の牡蠣小屋は他より安く美味しいので、大切に守っていただきたいです。
これからも毎年伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
回答要旨
ご要望の件については、バス停の管理者であり運行事業者である昭和自動車株式会社にお願いいたしました。
また、JR筑肥線の駅から牡蠣小屋に向かうアクセスについて、どこからどのバスに乗れば便利かという情報を、糸島市観光協会、糸島漁業協同組合及び各牡蠣小屋がインターネットやチラシなどで毎シーズン周知されていますので、ぜひご利用ください(下記アドレスをご参照ください)。来シーズンもぜひ当市の牡蠣をご堪能ください。
【参考】
糸島市観光協会ホームページ
トップページ:https://kanko-itoshima.jp
牡蠣小屋関係のページ:https://kanko-itoshima.jp/spot/itoshima-oyster-2023-2024/
糸島漁業協同組合ホームページ
トップページ:http://foitoshima.jf-net.ne.jp
牡蠣小屋関係のページ:http://foitoshima.jf-net.ne.jp/kaki
子どもの医療費助成の拡大について
子ども医療費助成を拡大していただきたいです。
福岡市では、令和6年1月1日より、高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで、学生でない人も対象、保護者の所得制限なし)となりました。
糸島市は、令和元年10月1日より中学3年生まで(所得制限の廃止)拡大されましたが、やはり、子育て世代といたしましては高校生まで拡大していただけると助かります。
今後拡大される予定はありますでしょうか?
回答要旨
病院を受診したときに病院受付で支払うお金(医療費自己負担額)には福岡県内で統一された基準がありますが、福岡市の自己負担上限額500円のように、自治体によっては独自のサービスを行っているところもあります。
自己負担額の助成拡大や助成対象の範囲拡大をするには、拡大した分だけの財政負担が伴います。糸島市でも、独自サービスとして高校生世代まで対象を拡大した場合など、様々な場合で試算を行っていますが、その財政負担は大きく、子ども医療費助成制度については現状維持(中学生世代まで)となっています。
市としての政策を検討する場合は、子ども医療費助成制度などの子ども・子育て分野だけでなく、高齢者や障がい者の分野、公園や道路整備、ゴミなどの生活環境の分野、農林水産業や観光の分野など、まちづくりを総合的に考え、財政面、緊急性など優先順位を判断しています。
特に財政面は慎重な判断が必要であり、「次世代の子どもたち」に借金をできるだけ残さないよう、糸島市の健全経営に努めているところです。